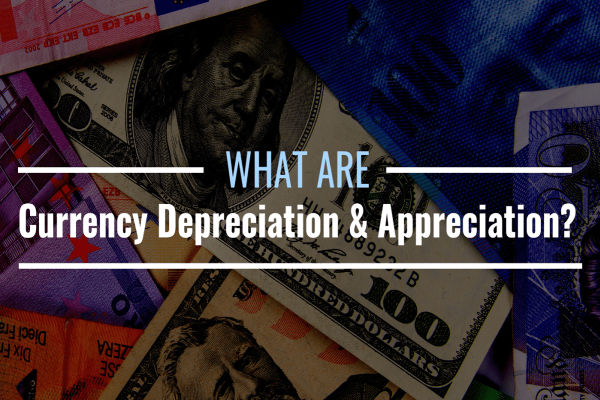キャンペーン
公開日: 2025-11-03

日本はエネルギー資源が乏しく、使用する原油のほとんどを海外から輸入しています。そのため、どの国から原油を調達しているかは、日本の経済や産業活動、そしてエネルギー安全保障に直結する重要な問題です。現在は中東地域への依存度が非常に高く、国際情勢の影響を受けやすい構造となっています。
本記事では、日本の原油輸入先を「国・地域別の現状」「過去からの変化」「今後のリスクと対策」という3つの視点からわかりやすく整理し、日本が直面する課題と今後の方向性を探ります。
日本の原油輸入先の現状

日本の原油輸入は、圧倒的に中東地域に依存しています。最新の統計によると、全輸入量の約94.7%が中東諸国から 供給されており、この構造は長年大きく変わっていません。日本は資源が乏しいため、海外からの安定供給に依存せざるを得ない状況が続いています。
国別に見ると、アラブ首長国連邦(UAE) が最も大きな供給国で、全体の約40.9% を占めます。次いで、サウジアラビア が 約39.4%、クウェート が 約8.2%、カタール が 約4.5% となっています。つまり、わずか4か国で日本の原油輸入の9割近くを占めているのが現状です。
この構造は、単に価格の問題ではなく、長期的な供給契約や信頼関係の積み重ねによって形成されてきました。中東諸国は豊富な埋蔵量を持ち、国際的にも安定した輸出国として位置づけられており、日本にとって信頼性の高いパートナーとなっています。
さらに、地理的にも日本から比較的近く、海上輸送ルート(特にホルムズ海峡経由)が確立している点も大きな要因です。
最近では、2024年にUAEがサウジアラビアを上回り、日本の最大の原油供給国となった ことが注目されました。これは、UAEが生産拡大を進め、日本企業とのエネルギー協力を強化していることの表れです。一方で、依然として中東への依存が高い構造に変わりはなく、地政学的リスクへの懸念も根強く残っています。
このように、日本の原油輸入は中東を中心に安定している一方で、供給の集中という課題も抱えています。今後は、エネルギーの多様化や再生可能エネルギーとの併用が、国家的なエネルギー戦略の鍵となるでしょう。
歴史的な変遷と多角化の試み
日本の原油輸入構造は、過去50年以上にわたって大きな変化を経験してきました。とくに1970年代の「第一次・第二次オイルショック」は、日本のエネルギー政策に強い衝撃を与え、輸入先の多様化や安定供給の確保が国家的課題となりました。
1960年代後半、日本の中東依存度は約91.2%(1967年度)に達していました。当時はサウジアラビア、イラン、クウェートなどが主要な供給国であり、日本のエネルギー基盤はほぼ中東に支えられていたといえます。
しかし、1973年の第一次オイルショックでは、アラブ産油国による禁輸措置が発動し、日本経済は大きな混乱を経験しました。これをきっかけに、日本政府と企業は「エネルギー安全保障」を最優先課題とし、原油輸入先の多角化政策を積極的に進めていきます。
1980年代にかけては、インドネシアや中国などアジア地域からの輸入拡大が進み、また北海(イギリス、ノルウェー)やメキシコなど非中東地域からの輸入ルートも開拓されました。その結果、1987年度には中東依存度が67.9%まで低下し、一時的に「脱・中東依存」の流れが実現しました。
しかし、1990年代以降になると、アジア各国の産油量が減少し、また価格面でも中東産原油の優位性が高まったことで、再び中東依存が進みます。特に2010年代後半には中東依存度が92~93%前後にまで上昇し、ほぼ元の水準に戻りました。これは、アジアやロシアからの供給が限定的であったこと、また中東諸国との長期契約が安定的に機能していたことが背景にあります。
さらに、ロシアや米国、エクアドルなど中東以外の国からの輸入も試みられましたが、量的には限定的でした。ロシア産原油は地理的な制約や政治的リスク、米国産は価格や輸送コストの問題などがあり、継続的な代替には至っていません。
結果として、日本の原油自給率は現在も約0.3%程度にとどまっており、依然として海外への依存度が極めて高い状態が続いています。このため、日本は原油の輸入多角化だけでなく、エネルギー構造そのものの転換(再生可能エネルギーの拡大や水素燃料の導入など)を進める必要があるとされています。
日本の原油輸入先構造が抱えるリスク・課題
日本の原油輸入先構造は長年にわたり中東地域への依存が続いており、この構造には複数のリスクと課題が内在しています。特に地政学的リスクや輸送ルートの安全保障、価格変動への脆弱性などは、国家レベルでの安定供給に直結する重要な懸念点です。
地政学リスク ― ホルムズ海峡という「生命線」
日本が輸入する中東原油のほとんどは、ペルシャ湾からホルムズ海峡を経由して海上輸送されています。この海峡は世界の原油輸送量の約2割が通過する「世界のチョークポイント」と呼ばれる海上交通の要所です。
しかし、イランや周辺諸国との緊張、テロリズム、軍事衝突などのリスクが常に存在し、もし航行が制限されれば、日本への原油供給に深刻な影響が及びます。たとえば2019年には、ホルムズ海峡付近で日本関連のタンカーが攻撃を受けた事件もあり、こうした脆弱性が改めて注目されました。
輸送インフラ・海上シーレーンの安全性
日本のエネルギー輸入は、タンカーによる長距離海上輸送に大きく依存しています。したがって、海賊行為や海難事故、自然災害などによる輸送の中断リスクも無視できません。
政府は「海上交通路(シーレーン)の安全確保」を国家安全保障の柱と位置づけ、自衛隊や同盟国との連携による警備活動を強化していますが、気候変動による異常気象や国際紛争の拡大など、リスク要因は年々複雑化しています。
輸入先の集中によるリスク ― 価格・交渉力の問題
中東4か国(UAE、サウジアラビア、クウェート、カタール)で約9割を占めるという輸入構造は、供給面での安定をもたらす一方、価格交渉力の低下 という弱点を抱えます。
供給国が減産を決定した場合や、OPEC(石油輸出国機構)の政策変更があった場合、日本はその影響を直接受けやすく、国内のガソリン価格や企業のエネルギーコストにも即座に反映されます。
特に近年は、OPECプラス(OPEC+非加盟国)の協調減産や原油先物価格の変動が激しく、こうした国際的な価格調整の波を吸収しづらいという構造的問題を抱えています。
国内需要の変化と構造転換とのギャップ
国内では電動車の普及や再生可能エネルギーの導入拡大が進み、原油の国内消費量は減少傾向にあります。しかし、エネルギー転換は一朝一夕には進まず、依然として運輸・化学・製造などの基幹産業は原油を主要エネルギー源として依存しています。
このため、需要構造が変化しても、輸入依存度の高さや契約構造はすぐには変えられず、「需要の減少」と「供給の集中」 の間でバランスを取ることが難しくなっています。
為替・国際価格の影響 ― 経済への波及
原油取引はドル建てで行われるため、円安局面では輸入コストが急上昇します。たとえば円相場が1ドル=150円を超えるような状況下では、原油価格が安定していても実質的な負担は大きくなります。
また、国際的な原油価格(ブレント原油やWTI)の変動も日本経済に直接影響します。原油価格の上昇は燃料代や電力コストを押し上げ、企業収益や消費者物価にも波及します。
このように、為替リスクと原油価格リスクの“二重構造” が日本経済の不安定要因となっており、エネルギー価格変動がそのままインフレ圧力として作用する点が課題です。
日本の対応・戦略的観点

日本は中東への原油依存が高いという構造的な課題を抱えつつも、そのリスクを軽減するために多方面から対策を講じています。政府・企業・研究機関が連携しながら、「輸入先の多様化」「輸送ルートの安全確保」「備蓄強化」「脱炭素化の推進」 など、エネルギー安全保障と経済合理性の両立を目指しています。以下では、その主要な戦略を整理します。
① 輸入先の多様化 ― “脱・中東依存” への長期的挑戦
日本政府は長年、「中東依存からの脱却」を掲げ、輸入先の地域・国・原油種類の多様化を進めてきました。
その一環として、アジア・アフリカ・アメリカ大陸など、中東以外の産油国との関係強化を図っています。特に米国産シェールオイルや、アフリカのアンゴラ・ナイジェリア など新興供給国との取引が検討されており、実際に小規模ながら輸入が始まっています。
また、輸入原油の種類も「軽質油」だけでなく、「重質油」や「低硫黄原油」などの多様な性質の原油を扱えるよう、精製施設の技術改善 も進められています。
とはいえ、これらの動きは中東依存を一気に変えるほどの規模には至っておらず、現実的には「中東中心+補完的な他地域」という形で段階的な分散を目指しているのが実情です。
② 輸送ルートの確保と代替ルートの模索
ホルムズ海峡に依存する現在の輸送ルートは、地政学的リスクが集中しています。日本はこのリスクを分散するため、インド洋経由ルートや東南アジアを経由する新ルートの検討、および**輸送船の多様化(大型化・最新型タンカー導入)**を進めています。
また、政府は「海上交通路(シーレーン)」の安全確保を国家安全保障の一環と位置づけ、自衛隊や米国・オーストラリア・インドなどとの連携強化(いわゆる「自由で開かれたインド太平洋」構想)を通じて、海上警備活動を強化しています。
さらに、アジア諸国間での共同備蓄・共同輸送ネットワーク の構想も進んでおり、有事の際に複数国で融通できる仕組みづくりが模索されています。
③ 国内精製・ストック(備蓄)戦略
供給途絶に備えるため、日本は国家備蓄・民間備蓄の二本柱で原油の在庫を管理しています。
国家備蓄としては、全国の沿岸部にタンクや地下備蓄基地を整備しており、約160日分の消費量に相当する原油を確保しています。これに加え、石油会社などによる民間備蓄が約90日分あり、合計で250日分以上の備蓄体制を保っています。
この備蓄は、国際エネルギー機関(IEA)の基準(90日分)を大きく上回る水準であり、日本の危機管理能力の高さを示しています。
また、国内の製油所・精製設備の近代化も進められており、輸入原油の品質や種類に応じて柔軟に生産ラインを切り替えられるよう、技術的対応が整備されています。
④ 再生可能エネルギー・脱炭素化への転換
原油への過度な依存を減らすため、日本は「2050年カーボンニュートラル」達成を目標に、再生可能エネルギー・水素・アンモニア燃料の導入を加速しています。
政府は2030年までに再生可能エネルギー比率を36〜38%へ引き上げる方針を掲げており、太陽光・風力・地熱の拡大に加え、EV(電気自動車)普及や水素エネルギーの社会実装を推進しています。
これらの取り組みは直接的な原油輸入量を減らすことにつながり、長期的にはエネルギー構造の転換=原油依存低減という形でリスクを軽減していく戦略です。
さらに、製造業・運輸業などの分野でも燃料転換(脱石油化) が進みつつあります。
⑤ エネルギー外交と産油国とのパートナーシップ強化
完全な「脱中東」は現実的ではないため、日本は中東産油国との関係をむしろ「戦略的パートナーシップ」 として深化させる方向に動いています。
サウジアラビアやUAEとは、単なる原油輸入国・輸出国の関係を超え、水素・アンモニア燃料などの次世代エネルギー開発における協力関係を構築しています。
2023年には、UAEと「グリーンエネルギー分野での包括的協力覚書」を締結し、化石燃料に代わる脱炭素エネルギーの共同開発が進められています。
このように、日本は「量的な多様化」だけでなく、「質的な協力強化」を通じて、安定供給とエネルギー転換を同時に達成する戦略を描いています。
結論
日本の原油輸入先は、依然として中東地域が主要で、地政学的リスクを大きく抱えています。こうした状況を踏まえると、エネルギー供給の安定確保と多様化が今後の重要課題となります。
読者として注目すべきポイントは、①サウジアラビアやUAEなど主要輸入国の政策動向、②ホルムズ海峡など海上輸送ルートの安全確保、③再生可能エネルギーや脱炭素政策の進展です。
最終的に、日本のエネルギー戦略は「安定供給」と「環境対応」を両立させる方向に進む必要があり、原油輸入構造の見直しがその鍵を握っています。
免責事項: この資料は一般的な情報提供のみを目的としており、信頼できる財務、投資、その他のアドバイスを意図したものではなく、またそのように見なされるべきではありません。この資料に記載されている意見は、EBCまたは著者が特定の投資、証券、取引、または投資戦略が特定の個人に適していることを推奨するものではありません。